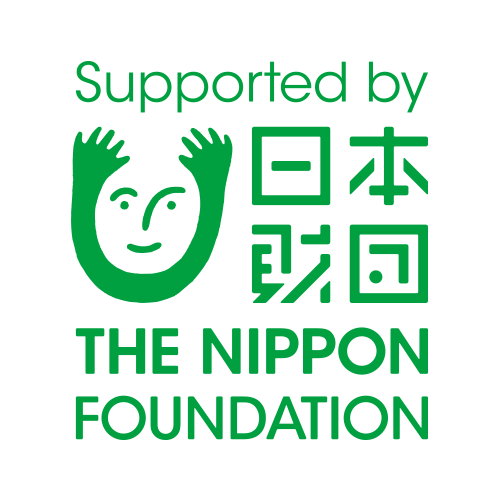TOPICS on the Ocean
ごみになると分解が始まるプラスチック
安くて丈夫、用途に適した多くの種類があって、いろいろな形を自在に作れるプラスチック。わたしたちの生活を支えているこの便利な人工素材は、ごみとなって街や海などの環境中に出てしまうと、いつまでも消えない「永遠のごみ」になる。その丈夫さがあだになり、小さく砕けていってもいつまでもプラスチックのまま。木や紙などの天然素材のように最後は二酸化炭素と水に分解されて消滅するということがない。
なぜ木材は消滅するのか。それは、木を分解する菌類などの生き物たちがいるからだ。木に取り付いた生き物がつくる物質で木の成分が分解され、できた細かい分解物をバクテリアなどの微生物が食べて二酸化炭素と水にしてしまう。自然界は、最終的に微生物が食べられる極微のサイズにまで木の成分を分解するしくみを、長い地球の歴史のなかで備えたのだ。
プラスチックは、炭素の原子が鎖のように長くつながってできている人工の「高分子化合物」だ。炭素のつながりが構造の基本になっている点は、木材とおなじだ。だが、プラスチックが広くわたしたちの生活に使われるようになって、まだ半世紀あまり。ごみとなったプラスチックの「炭素の鎖」を細かく切って微生物が消費できる大きさに分解してくれる生き物が、ほとんどいない。
だからといって、炭素の鎖がもともと切れやすいプラスチックを作ったのでは、製品として使っているあいだにもろくなって実用に耐えない。使っているときは従来どおりに丈夫なプラスチックで、環境中にごみとして放置されたときだけ炭素の鎖が切れて、木材のように消滅するプラスチックはできないものか。そんな都合のよいプラスチックなどあるのだろうか。
海底に沈むと分解が始まる
群馬大学の粕谷健一教授の研究グループは、ごみになったときだけ「炭素の鎖」が切れ始めるプラスチックの研究を、ここ10年ほど進めている。研究グループの橘熊野准教授らが2017年の論文で発表したプラスチック、そして筒場豊和特任助教らが今年3月の論文で発表したプラスチックは、いずれも酸素不足の「還元環境」に置かれると炭素の鎖が切れる。使っているあいだはふつうのプラスチックなのに、還元環境にさらされると「分解のスイッチ」がオンになるのだ。
なぜ還元環境に注目するのか。それは、海のプラごみがたどり着く先に、この還元環境があると考えられているからだ。
いま陸域から大量のプラごみが海に流れ込んでいる。1年間で480万~1270万トンに達するという推定もある。だが、海面などを漂っているプラごみは、それに比べてきわめて少ない。多くは沈んでしまったというのが、ひとつの有力な考え方だ。実際に、深海底でもプラごみは確認されている。

水深1554メートルの駿河湾海底に沈んだプラスチックごみ(海洋研究開発機構提供)
そして海底の泥の中が、まさにこの還元環境なのだ。沈んだ生き物の死がいなどが分解される過程で、海底の泥の中は酸素が不足した状態、すなわち還元環境になっている。中学の理科で習う「酸化と還元」の還元だ。プラごみが空気中や海水中にあるうちはまだ周囲に酸素があるが、海底の泥に入ると一転して酸素不足の還元環境になるわけだ。
海底の還元環境で炭素の鎖が切れるプラスチックができれば、海底に沈むプラごみは「永遠のごみ」ではなくなるかもしれない。そこに微生物がいれば、細かく切れた鎖の断片を食べて、二酸化炭素と水にまで分解してくれるからだ。
生分解性プラスチックに分解スイッチを組み込んだ
筒場さんらが開発したのは、生分解性プラスチックの「ポリブチレンサクシネート(PBS)」に分解スイッチを組み込んだプラスチックだ。
生分解性プラスチックは、PBSやポリ乳酸などいくつかの種類が知られている。一般のプラスチックとは違い、菌類がだす物質などと微生物のはたらきで木材のように二酸化炭素と水にまで分解される。
だが、それには「土の中」「堆肥づくりで60度以上の温度」といった特殊な条件が、その種類ごとに求められる。畑地を覆う農業用フィルムをPBSで作ると、PBSは土中で分解されるので、使用後は回収せず土に混ぜ込むだけで処分できる。だが、海中では分解されない。
筒場さんらは、PBSの「炭素の鎖」のところどころに硫黄原子2個のペアを組み込んだ新しいプラスチックをつくった。海底の泥の中の還元環境を再現した液体にこのプラスチックを入れて室温で9日間置いたところ、炭素の鎖が短くなっていることが確認された。硫黄原子のペアが分解スイッチとしてはたらき、炭素の鎖が切れたのだ。還元環境でない場合は、炭素の鎖は切れなかった。
さらに、このプラスチックで厚さ0.1ミリメートルのフィルムをつくり、還元環境の液体に5週間つけたところ、重量が32%減った。炭素の鎖が切れて細かくなった断片が、液体に溶け込んだのだ。もしここに自然界と同様に微生物がいれば、溶け込んだ断片を微生物が食べて二酸化炭素と水に分解した可能性がある。これもやはり、還元環境でない場合は、重量は減らなかった。
また、合成方法を改良し、これまでのプラスチックに近い柔軟性と強度をもたせることにも成功したという。

筒場さんらのプラスチックは、従来品に近い柔軟性と強度をもっている(粕谷教授の研究グループ提供)
研究成果をどう社会に生かしていくか
海に流れ込んだプラごみは、海岸に漂着したものなら拾って掃除することができる。だが、海底に沈んでしまったプラごみは、現実的には回収不可能だ。このままだと、海底は「永遠のごみ」だらけになってしまう。粕谷さんらの研究は、その難題の解決に手がかりを与えるものだ。
もちろん、筒場さんらが開発したプラスチックが、そのまますぐに実用化されるわけではない。実験室ではなく実際の海底でほんとうに分解されるのかがわかっていないし、かりにそれがうまくいっても、コストの問題もある。理想的な還元環境をもつ海底が世界の海にどれくらい広がっているかも、はっきりしない。これからの検討課題だ。
粕谷さんらの研究は、プラごみ問題の解決に向けた有力な持ち駒をひとつ増やしてくれた。そして、それを現実にどう生かしていくかは、社会が決めることだ。
生分解されるプラスチックは、細かく崩れやすいプラスチックともいえる。大きさ5ミリメートル以下のマイクロプラスチックが、人間を含む生き物の体に取り込まれていることは、すでに知られている。その悪影響を調べる研究も進行中だ。もちろん、ふつうのプラスチックもマイクロプラスチックになるが、そのなかで生分解性プラスチックのメリットをどう活用していけばよいのか。
生分解性プラスチックは二酸化炭素に分解されるというが、その点は、地球温暖化を進める一因とされている焼却処分とおなじことだ。二酸化炭素と水に分解されて消滅するというごみとしてのメリットをとるか、地球温暖化やマイクロプラスチックの問題につながるデメリットを重くみるか。
深い海は一般に土の中より温度が低く、微生物も少ない。分解に不利なそうした場で分解するプラスチックに、土中で分解する生分解性プラスチックとおなじような素早さで消滅する性能を求めるのは現実的なのかという問題もある。
生分解して消滅するプラスチックといえども、社会への実装に向けて考えるべきことはいろいろある。これをわたしたちはどう使うべきなのか。その方向を科学の成果に基づいて定めるためにも、こうした研究に注目し、プラごみ問題への関心を持ち続けたい。
文責:サイエンスライター・東京大学特任教授 保坂直紀