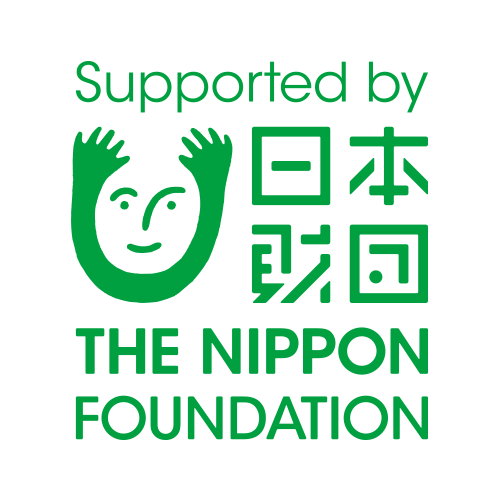TOPICS on the Ocean
養殖ウナギは川で生き残れない
やはり、甘ったれた環境で育ったヤツは生き残れないということなのか。科学の研究成果に人間の生き様を投影するのは禁物だが、どうしてもわたしたちの社会に重なって見えてしまう。ウナギについてのそんな論文が発表された。養殖場で餌をたっぷり与えられて育ったウナギは、川に放流しても、2年後に生き残っていたのは5%だったのだ。
二ホンウナギは、日本からはるか南に3000キロメートルも離れたグアム島の西方海域で生まれ、黒潮などの海流に乗って日本にやってくる。それが川に入って成長する。だが、そうした天然ウナギは激減している。養殖場で卵を産ませて育てる「完全養殖」は、いまはまだ研究段階なので、海岸でつかまえたシラスウナギ、つまり子どものウナギを養殖場で育てて成魚にして出荷したり、地元の漁業協同組合などが資源保護のために川に放流したりしている。

二ホンウナギ(写真はいずれも脇谷さん提供)
今回は、その放流のお話だ。2018年に国内の河川などで捕獲された二ホンウナギが69トンなのに対し、その半量近い30トン、数にして約200万匹が放流された。ところが、そうした二ホンウナギの放流の効果を調べた科学論文は、これまでにないのだという。「放流しても、どうもあまり効果はないのではないか」という推測も一部にはあった。それを初めて科学的な手法で検証したのが、脇谷量子郎・東京大学大気海洋研究所特任研究員、中央大学などの研究グループだ。
2年後の生き残りウナギは5%
脇谷さんらは、養殖した二ホンウナギを放流事業の行われていない国内の4河川に放流し、2年間にわたって経過を観察した。4河川のうち南寄りの鹿児島県の貝底川、静岡県の波多打川には天然ウナギが多く、それより北に位置する福井県の三本木川、青森県の長沢川には、天然ウナギがほとんどいない。2016年に予備調査を行い、2017年6月に1940匹を放流した。放流時には、どの川のウナギも全長を約30センチメートル、体重を約30グラムにそろえた。

「電気ショッカー」を使った鹿児島県貝底川での調査。
ウナギの数は、それぞれの川に設定した調査区域で「電気ショッカー」とよばれる器具を使い、一時的に動きを低下させたウナギを拾い集めて調べた。その結果、2年後に生き残っていた放流ウナギ、すなわち一定面積あたりで確認できた放流ウナギの数は、4河川全体で5%だった。天然ウナギがいる川といない川とで、その数に違いはなかった。
生き残っていた数に違いはなかったが、別の違いがみつかった。天然ウナギがいる貝底川、波多打川に放流したウナギは、体重が増えなかったのだ。この研究で最後に捕獲した時点の体重をもとに計算すると、放流時に比べて、体重が1か月(30日)あたり貝底川で1.6グラム、波多打川で2.3グラムの割合で減っていた。数が激減するうえに、生き残ってもやせ細ってしまうのだ。
それに対し、天然ウナギがほとんどいない長沢川では3.5グラム、三本木川では10.5グラムの割合で増えていた。餌になる小エビなどウナギ以外の生き物の量は、4河川でほとんど差がないことが確かめられている。となると、天然ウナギのいる川では、放流ウナギは育ちにくいということなのか。天然ウナギの存在が、放流ウナギの成長を妨げているのだろうか。
この実験は、自然の河川で行っている。現実の放流によく似た状況を再現できる利点がある一方で、たとえば、天然ウナギが放流ウナギになにか意地悪をしているのかを細かく観察することはできない。また、その規模や餌になる生き物の量などが大きく違わない4河川で比較しているとはいえ、「それは天然ウナギの有無ではなくて、この研究では気づいていない河川の性質の違いが原因ではないか」と指摘されれば、それに説得力のある答えを返すのは難しい。
その点をあきらかにするため、脇谷さんらは、人工池や水槽を使った観察も行っている。これならウナギの行動をつねにウォッチできるし、生育環境を完全に整えて比較できる。
養殖ウナギは天然ウナギと一緒だと育ちにくい
人工池を使った実験では、屋外にある三つのコンクリート水槽を使った。大きさはいずれも縦8メートル、横4メートルで、水深は1.5メートル。水温変化の少ない地下水を使っていたため、水温は季節を問わず25度に保たれていた。
このうち二つの水槽には、天然ウナギと養殖ウナギを5匹ずつ、残りの水槽には、これらと比較するため養殖ウナギだけを10匹入れた。餌のエビも水槽間で違いがでないように与えた。2014年10月から2016年10月までの2年間、3か月ごとに水を抜いてウナギの生存を確認し、成長のようすを調べた。

天然ウナギと養殖ウナギを1匹ずつ水槽に入れた実験。塩ビ管に入っているほうが天然ウナギ。
その結果、養殖ウナギだけの水槽では、1か月あたり体重は10グラムほど増えていたのに対し、天然ウナギと一緒に入れた養殖ウナギの体重は、その3分の1しか増えていなかった。また、この2年間で天然ウナギは1匹も死ななかったのに、天然ウナギと一緒の養殖ウナギは計10匹のうち6匹が死んでしまった。養殖ウナギだけの水槽では10匹のうち9匹が生き残ったので、天然ウナギと共存した水槽では生き残り率が低かったことになる。やはり、養殖ウナギは、天然ウナギと一緒だと生きにくいらしい。
では、天然ウナギは養殖ウナギになにか悪さをしているのだろうか。
天然ウナギと養殖ウナギの性質の違いは、室内の水槽で観察してわかった。水槽の底には、ウナギが1匹だけ入れる太さ1.6センチメートル、長さ20センチメートルの塩ビ管を沈めた。そして、天然ウナギと養殖ウナギ1匹ずつのペアを、いくつも並べた別々の水槽に入れた。天然、養殖ともに、全長は36センチメートル前後、体重は45グラム前後にそろえてある。これを14ペアについてビデオ録画もして観察した。
天然ウナギは攻撃的だった。塩ビ管は隠れ家として好適だが、1匹しか入れない。もし先客がいる塩ビ管に入りたければ、追い出すしかない。ウナギの典型的な攻撃方法は、相手にかみつくこと。このかみつき行動の頻度が、天然ウナギが1時間あたり5.7回だったのに対し、養殖ウナギは0.44回だった。養殖ウナギが天然ウナギにかみつくことは少なく、総かみつき回数の9割が、天然ウナギが養殖ウナギにかみつくケースだった。
また、塩ビ管のようすを計1233回確認したところ、その68%にあたる839回で塩ビ管にウナギが入っており、そのうち79%の666回は天然ウナギだった。天然ウナギの塩ビ管占有率は、養殖ウナギよりはるかに高い。塩ビ管で休んでいる養殖ウナギに天然ウナギがかみつき、追い出すシーンも観察されたという。
天然ウナギは攻撃性が強く、放流された川に先客の天然ウナギがいれば、そこは養殖ウナギにとって生きにくい環境なのだろう。天然ウナギがいるのだから、その川の生育環境はウナギにとって悪くはないとしても、当の天然ウナギが、もとはおなじシラスウナギの兄弟姉妹だった養殖ウナギの生育を妨げていることになる。
この方法で放流してもウナギは増えない
ウナギをとった川に、それを埋め合わせるかのように養殖ウナギを放流する――。ウナギの増殖事業にはさまざまな形があるが、この研究が対象としたこうした放流では、ウナギの量をおおきく増やすことは望み薄なようだ。
放流した養殖ウナギは、わずか2年間で5%に減っていた。二ホンウナギは、産卵のため海へ出ていくまえに川で10年くらい過ごす。2年といえば、そのほんの始まりだ。さらに減ってしまうかもしれない。すくなくとも、これより増えることはない。
今回の研究結果を単純に解釈すれば、養殖ウナギを放流するなら天然ウナギのいない川のほうがマシということにもなるが、脇谷さんによると、「本来とは違う育ち方をした放流ウナギが、はるか南洋の産卵場所にたどりつけるのか」という、そもそもの問題がある。もし、産卵の過程を含めた本格的な資源回復の役に立たないとすれば、ウナギの放流はいったいなにを目的に行っているのかという問題だ。
また、海に出たのち生まれた川に戻ってくるサケとは違い、海で生まれたウナギは、親ウナギがいた川に戻るわけではない。どこかの川でウナギの放流に熱を入れても、資源回復の効果や実態を確認するのは難しい。
生き残り率の「5%」という数字についても、その意味合いは、じつははっきりしていない。天然ウナギにしても、川にたどり着いたシラスウナギのうち成長できるのは、ほんの一部のはずだ。放流ウナギが2年後に「5%しか生き残っていなかった」のか「5%も生き残っていた」のかは、現段階ではなんとも言い難いという。
養殖ウナギは、天然のシラスウナギを人工的に育てただけなので、川育ちの天然ウナギとまったく同一の種だ。違いは、そのまま自然の川で成長したか、養殖場で育てられたかという点だけ。半年ほど養殖場で育てられたウナギは、天然ウナギに比べて生存のための競争力が劣っていた。共存すると、現実に成長がかんばしくなかった。今回の研究でわかったのは、そういうことだ。
脇谷さんは「今回の研究は、二ホンウナギの放流を科学的に考えていく第一歩だ」という。養殖場での育て方の改善。より放流に適した環境の探索。さらには、養殖場で大きく育てて「養殖もの」として出荷するのか、あるいは、かりに本格的な資源回復にはあまり役立たないとしても、川で捕獲できる「天然もの」を放流により増やすことにこだわるのかといった社会的な側面。二ホンウナギの放流について考えるべきことは、たしかにたくさんある。
考えてみると、こうして世間に関心をもたれるウナギは、まだ幸せなのかもしれない。生息環境の悪化で人知れず命脈が尽きてしまう生き物たちも、自然界にはたくさんいるのだから。
文責:サイエンスライター・東京大学特任教授 保坂直紀