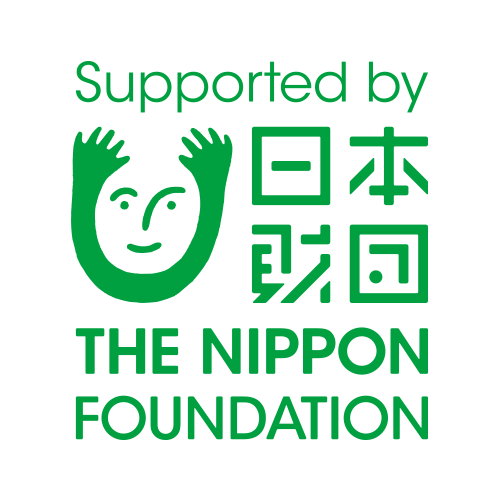TOPICS on the Ocean
ウミガメで3か月先の天候を予測する
毎日の天気予報をはじめ、将来の天候を予測するために使われるのが、コンピューターによるシミュレーションだ。大気の流れや気温などの変化を計算するためのたくさんの方程式を組み合わせ、いまの状態をもとにちょっと先の状態を計算し、それをもとに、また少し先の状態を計算し……という手順を繰り返していく。
そのとき、海面の熱は大気に伝わってその動きに影響を与えるので、天候について知りたいときでも、海面の水温を考えに入れなければならない。数日先までの天気の予報なら、海面水温はそうおおきく変化しないので、観測にもとづく現在の状態を変えずにそのままにしておいてよいが、数か月先の天候を予測するときは、海面水温の変化も同時に計算していかなければならない。大気より海のほうが熱をたくさん蓄えるので、むしろ海面水温を的確に予測することが大切だ。
海面水温の的確な予測のためには、現在の海面、海中の状態を正確に把握することが必要だ。これが難しい。海面の水温は人工衛星から観測したデータが使えるので、まだいい。問題は海中の水温だ。そのために、「アルゴ」とよばれる国際的な観測システムが運営されている。世界中の海に水温センサーなどがついた浮沈式のブイを4000台近く投入し、現在の海中の状況をつねに観測している。ところが、このブイにも泣き所がある。海面から水深2000メートルまでを上下する仕様なので、陸地に近い浅い海は苦手なのだ。そこで登場するのがウミガメである。
ウミガメが水温を測る
海洋研究開発機構アプリケーションラボの土井威志研究員、東京大学大気海洋研究所の佐藤克文教授らの研究グループが注目したのは、ヒメウミガメだ。熱帯の海でくらすヒメウミガメは、海底のえさをあさるため、他のウミガメに比べて深くまで潜る習性がある。佐藤さんの専門は、生き物の体にセンサーやカメラを取りつけてその生態を研究する「バイオロギング」だ。5匹のヒメウミガメの背に接着剤で水深と温度などのセンサーを取りつけ、ニューギニア島の西端に位置するインドネシア西パプア州のワルマメディ海岸から2017年6月に放した。すると、ヒメウミガメたちは広い太平洋には出ていかず、南下して、オーストラリアとの間に挟まれた比較的狭いアラフラ海に入っていった。
このセンサーは約0.1度の誤差で海中の水温を観測し続け、記録したデータを人工衛星経由で送ってくる。放したウミガメは水深100メートル以上もの深いところまで潜っていた。ウミガメの背にあまり大掛かりなセンサーは付けられないので、測定精度はアルゴなどの機器観測に比べると、やや悪い。だが、アルゴなどが不得意な海域を補完できる可能性もありそうだ。ウミガメは、どれくらい海面水温の予測精度を上げられるのか。土井さんは、それを調べた。

砂浜で産卵を終えて海に戻るヒメウミガメ。背中に水深、水温の記録を人工衛星へ送る発信器が取りつけてある。発信機は1~2年で自然に脱落するという。2019年6月、インドネシア西パプア州のワルマメディ海岸にて。(佐藤克文氏撮影、海洋研究開発機構・東京大学のプレスリリースより)
予測の誤差が大幅に小さくなった
土井さんは、このウミガメの観測データを利用した場合と利用しない場合とで、シミュレーションの正確さがどれくらい変わるかを調べた。2017年8月の海の状態からスタートし、その年の11月の海面水温をコンピューターによる計算で予測してみたのだ。ウミガメのデータが使われるのは、計算の起点となる8月の海の状態を決定する部分だ。ここに、人工衛星による海面水温の実測値などに加えてウミガメのデータを組み込んだ。
11月の水温を「予測」するとはいっても、実際にはすでに人工衛星から観測した実測データが手元にあるので、それとこの「予測」を比べ、どれだけ正確に予測計算ができるのかを検証するわけだ。その結果、アラフラ海の海面水温については、ウミガメのデータを利用すると、利用しない場合に比べて0.5度くらい予測精度が上がることがわかった。
「0.5度」という値は、小さいようだが、熱帯の海では大きな意味をもつ。世界の各地に高温や少雨などの極端な気象をもたらすエルニーニョは、東太平洋赤道域の海面水温が平年より0.5度高くなっていることが判定基準になっている。熱帯低気圧が発達して台風になるかどうかも、海面水温が26~27度より高いか低いかという微妙な温度差に左右される。熱帯の海の「0.5度」は、けっして小さな数字ではない。
せっかくのデータを徹底的に使う
いま科学の世界では、一般市民が科学者とともに研究を進める「シチズンサイエンス」が生まれつつある。雪が降ったとき、その結晶をスマートフォンで撮影して研究者に送り、その形から上空の気温などを推定して気象学の研究に役立てる。そんな研究が、実際に進められている。プロの研究者が手間と時間、それに多額の費用をかけて行う観測に比べれば、その精度は悪く、データの質も観測者によってさまざまだ。だが、これまでの観測で欠落していたデータを補うことができるなら、それもじゅうぶんに科学的な価値をもつ。ようは、そのデータを使う目的と使い方なのだ。
プロの研究者と一般の人がとるデータ、おなじ科学でも分野が異なれば、データの収集や処理に求められる厳密さは違うのがふつうだ。土井さんたちの研究も、本来は動物の生態を研究するためのデータを、天候の予測という物理の分野で使えるのかを検証したことになる。その結果、「0.5度」もの精度向上をもたらす有効なデータとして使えることが確かめられた。まさにデータの異分野交流だ。
土井さんは「海洋観測のために作られたアルゴのような機器のデータは、海洋研究者のあいだで共有し、使えるしくみができあがっている。そこに、これまでになかったバイオロギングのようなデータが加われば、新たな研究が広がるという期待感がある」という。土井さんたちのような成功例を一つひとつ積み重ねていくことで、異分野のデータに新たな活用の道が開けるのかもしれない。せっかく苦労して取ったデータなのだから、徹底的に使いたいものだ。
※東京大学大気海洋研究所によるプレスリリースはこちらです。
文責:サイエンスライター・東京大学特任教授 保坂直紀