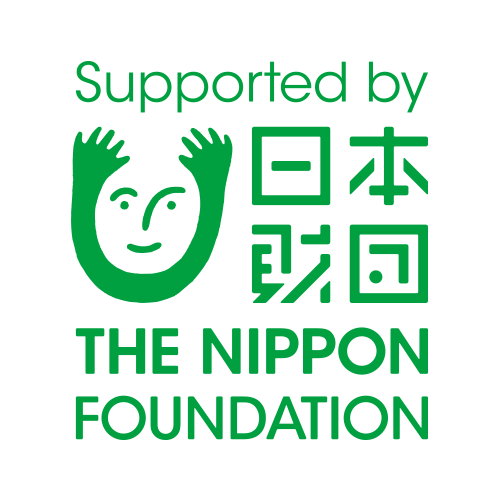TOPICS on the Ocean
生分解性プラスチックは、地球のプラごみ汚染を救うのか?
海や川の岸を歩きながら足元の砂を見ると、赤、青、緑など色とりどりの小さな破片が目に入る。小さく砕けたプラスチックだ。砂を掘っても、おなじようにプラスチック片がでてくる。砂に埋まってもろくなったレジ袋は、頭を出している部分を引っ張ると、そこだけ簡単に破れて袋は砂に残る。砂とプラスチックごみは、全体が一体化してしまっているのだ。ごみだけをより分けてすっかり回収することは、現実的にはもう難しい。
そんなとき頭をよぎるのが「生分解性プラスチック」だ。放置してもやがては分解されて消滅するプラごみ問題の救世主のように扱われることもある。国も、その研究と開発を推進していく考えだ。
だが、生分解性プラスチックに詳しい東京大学大学院農学生命科学研究科の岩田忠久教授は、「世間には誤解している方も多いように思う。『生分解性プラスチックがやがて広まって、プラごみ問題は一気に解決する』というわけではない」と説明する。すでに「環境にやさしい食器」などとして一部が実用化されてはいるが、どのような用途に適しているのかを市民一人ひとりがいまあらためて考え、その用途に最適な生分解性プラスチックを開発していく必要がある。

東京湾にそそぐ荒川の川岸(東京都江戸川区)でも、色とりどりの小さなプラスチック片が砂にたくさんまじっていた。(2019年9月撮影)
微生物がプラスチックを分解する
生分解性プラスチックとは、使用後に微生物によって分解され、最終的には水と二酸化炭素になるプラスチックのことだ。わたしたちがふつう使うプラスチックは、分解してくれる微生物がいないので、土や水の中のような自然界に放置すると、半永久的にプラスチックごみとして残る。生分解性プラスチックは、ごみになってもやがて消えてしまうのだから、使い方によってはたしかに有効だ。
日本ではあまり普及していないが、生ごみを微生物に分解させて「たい肥(コンポスト)」にする場合は、台所の水きり袋やごみ袋を生分解性プラスチックでつくっておけば、袋ごとたい肥づくりに回せる。農作物の苗を育てるポットを生分解性プラスチックでつくれば、それを畑に植えたとき、ポットはごみとして残らずに分解してしまう。
どこでも分解する万能プラではない
ただし、生分解性プラスチックは、どこでも分解が進むわけではない。この点が重要だ。岩田さんによると、「土の中」「海や川などの水の中」「コンポストづくり」のそれぞれに適したプラスチックは違う。「ポリ乳酸」というプラスチックは、温度が60度以上になるたい肥づくりでは1週間ほどで消滅するが、ふつうの土や水の中では分解しない。「ポリブチレンサクシネート」のプラスチックは、たい肥づくりや土中では分解するが、水の中では分解しない。

海で分解する生分解性プラスチックでつくった繊維を実際に海に沈め、その表面を撮影した電子顕微鏡写真。繊維の表面に小さな俵のような微生物がびっしりと張りついている。画面下の横棒の長さが100分の1ミリメートル。(岩田教授提供)
分解の主役は微生物だ。生き物だから、自らの活動に適した環境を選ぶ。ポリ乳酸の場合は、プラスチックを微生物が分解できる物質にあらかじめ変えておかなければならず、それに必要なのが60度以上という高い温度だ。酸素がじゅうぶんにある場所か、ほとんどない場所かで、活動する微生物も違う。土の浅いところには酸素があるが、3メートルも掘っていけば、そこはもう酸素不足だ。海中の場合、表層に酸素は多いが、水深1000メートルのあたりで少なくなり、それより深くなると、また酸素が増えていく。そのプラスチックがごみになったとき、どういう環境で分解させることになるのかを考慮に入れ、生産から使用、処理までのプロセス全体を計画しなければ、生分解性プラスチックを有効に使うことはできない。
バイオプラスチック?バイオマスプラスチック?
生分解性プラスチックに関連して「バイオプラスチック」「バイオマスプラスチック」という言葉があることも、生分解性プラスチックの意味合いをわかりにくくしている。とかく「環境にやさしい」というプラスイメージを与えがちな「バイオ」という言葉が、いろいろな意味で使われている。

生分解性プラスチックとバイオマスプラスチックをあわせてバイオプラスチックという。これがまず、わかりにくい。ここで「バイオ」とは、生き物に関係しているという意味だ。
生分解性プラスチックにとっての「バイオ」は、プラスチックが分解される過程の話だ。分解の主役が微生物であることを指している。プラスチックを分解して最終的に水と二酸化炭素にするのは微生物だし、その作業をしやすくする前段階の処理に、微生物が出す酵素が使われる場合もある。あくまでも、分解の過程が「バイオ」なのであって、そのプラスチックが何で作られているかには関係ない。植物のような生物由来の原料で作られるものもあるし、ふつうのプラスチックとおなじ石油由来の生分解性プラスチックもある。
バイオマスプラスチックの「バイオ」は、逆に、分解ではなく生産の過程を示している。そのプラスチックの原料が生物由来だという意味だ。「バイオマス」は「生物資源」のこと。ポリ乳酸の原料にはとうもろこしなどを使うし、微生物の体内で作られる物質を使うものもある。こちらは原料が「バイオ」なのであって、ごみとなったときに分解するか分解しないかは関係ない。分解するものもあるし、石油由来のふつうのプラスチックとおなじように分解しないものもある。
自然界の植物や動物はやがて土にかえるのだから、生物由来の原料を使ったプラスチックは、それとおなじように分解されて土にかえる――。この誤解は、おそらく自然のものは環境によいという思い込みとも関係があるのだろう。ラドン温泉で浴びる放射線は天然だから体によく、おなじ放射線でも原子力発電所の放射線は人工だから体に悪いといった誤解と同根かもしれない。「バイオ」はプラごみ問題を解決に導く魔法の言葉ではない。
「海」が生分解性プラスチックにとって有利な点
生分解性プラスチックは、速く分解すればよいというものではない。使っているときに分解しては困る。たとえば、農作物が若いときに畑の表面を覆うフィルムなら、不要になったら1か月くらいで素早くなくなってほしい。だが、乾燥した土地に水分を補う保水性のプラスチックとして使うなら、何年もの長期にわたって効果を発揮し、その後で分解されてなくなるのが理想だ。一般に生分解性プラスチックは、ふつうのプラスチックの何倍ものコストがかかるので、目的によほどうまく合致した製品でなければ、コストを乗り越えて社会に広まる動機が生まれない。
いまプラごみ流出が世界的な社会問題となっている「海」は、生分解性プラスチックの応用先として有利な点もあると岩田さんはいう。海には土に比べて微生物が少ない点だ。
たとえば、悪天候などによる流出が避けられない漁具。かごや網などの多くにプラスチックが使われており、ごみとなった後も海中で魚などを捕らえてしまう「ゴーストフィッシング」などで問題になっている。一般に海中には土の中ほどの微生物はいない。海中で分解するプラスチックを使っても、微生物は少ないので、そう速くは分解しない。海から揚げて微生物を洗い流せば、そう劣化はしないまま繰り返し使える。流出してしまったら、ゆっくりではあるが、やがては分解されてなくなる。
いま国内では年間1000万トンほどのプラスチックが生産されているが、生分解性プラスチックはその0.1%に満たない。しかも、ほとんどは海では分解しない。経済産業省は2050年をみすえて、海で分解するプラスチックの普及を目指している。
やはり基本は回収とリサイクル
「生分解性であろうとなかろうと、出てしまったプラスチックごみの基本は回収とリサイクルです。その努力をしても、どうしても環境中に流れ出てしまうものがある。そこに生分解性プラスチックを使う。プラスチック全体の1~2割といったところでしょうか」と岩田さんはいう。生分解性プラスチックは、最終的には水と二酸化炭素に分解される。プラスチックを燃やしても、出てくるのは水と二酸化炭素。結末がおなじなら、燃やして熱を利用したほうがましだという考え方もある。生分解性プラスチックだからといって、平気でポイ捨てするようになれば、それは本末転倒だ。回収とリサイクルという基本は守る必要がある。
海をはじめとするプラスチックごみの問題は、プラごみ単独で考えるわけにはいかない。燃やして処分したり、生分解性プラスチックが分解したりすると二酸化炭素が出る。リサイクルしやすくするために捨てる容器をお湯で洗えば、お湯をわかすエネルギーを余分に使うことになる。いずれも、地球温暖化防止のために二酸化炭素の排出を減らそうとする「パリ協定」に抵触する。プラごみの削減は、そういう苦しい選択の中で進めていかなければならない。
プラごみ問題は、それぞれの国や社会のしくみと深く結びついている。リサイクルにしても、そのための費用や労力を負担するのが難しい社会もある。だからこそ、市民がプラごみの実態をよく知ってアンテナの感度を高め、社会をすこしずつ動かしていくことが必要だ。生分解性プラスチックは、プラごみ問題の一側面に有効な解決策を与える可能性がある有望な素材だ。過度な期待を寄せることなく、その可能性と限界を見極めながら、社会全体でプラごみの削減に取り組みたい。
文責:サイエンスライター・東京大学特任教授 保坂直紀