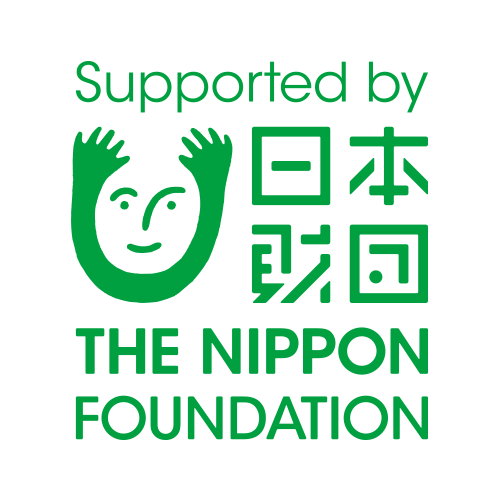TOPICS on the Ocean
海洋アライアンスのシンポで「海に生きる次世代を育てる」を議論(2023/10/10)
東京大学海洋アライアンス連携研究機構の第18回「東京大学の海研究」シンポジウムが10月10日、東京大学農学部弥生講堂を会場に「海に生きる次世代を育てる」のテーマで開かれた。
海は、現在と未来の地球環境と密接に結びつき、人間の文化や防災、資源などの面で私たちの生活に深く関わっている。とくに日本は広大な排他的経済水域をもち、その文化や産業は海なしには語りえない。
その一方で、たとえば日本の初等教育では海の扱いは小さく、海の役割り、暮らしとの関わり、世界を見る際の基盤としての大切さなどについての認識を、広く国民が共有しているとは言い難い。
こうした状況のなかで、海に関わる人材を東京大学はどう育てていくべきなのか。現在、学内で海洋教育に携わる9人の教員が実施中の教育プログラムを紹介し、学外からのゲストスピーカーを交えた計12人がこれからの展望について議論した。毎年秋に開催している「東京大学の海研究」シンポジウムは、新型コロナウイルス拡大の影響で2020年からはオンライン開催が続いたが、今回は4年ぶりに会場での開催となった。
「地球温暖化に挑む海洋教育」
(茅根創・東京大学大学院理学系研究科教授)
私が副センター長を務める教育学研究科付属海洋教育センターでは、海洋アライアンス内の組織だった前身の時代から、初等中等教育に海洋教育を広めるための活動を続けてきた。

そのなかでも、地球温暖化は重要なテーマだ。現在の学習指導要領では領土や領海といった側面が重視されているが、地球温暖化は防災や安全に関わる問題であり、なにより命にも関係している大切なテーマだ。
いまも進み続けている地球温暖化では、二つの事柄を考えておかなければならない。
一つは、これが世代間の問題だという点。とんでもない気候危機に直面することになるのは、いま初等中等教育を受けている若い世代だ。
もう一つは、地球温暖化「予測」という言葉の問題。この「予測」にあたる言葉として、国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」では「プロジェクション」が使われている。プロジェクションには、これからの道筋をほんの少し変えるだけで将来が変わるという能動的な意味が込められている。しかし、日本語で「予測」と言ったとき、それに対応するとふつう思われている「プリディクション」を思い浮かべると、これは科学的な予測であって、そこから将来を変えるという能動的な意味が失われてしまう。地球温暖化の予測は科学者の仕事であって、私たちはなにもすることができないと思ってはいけない。
漁業の盛んな町では、よくとれる魚種が変わることの背景には地球温暖化があるということを学ばせる。また、気象災害との関わりという点では、たとえば豪雨で浸水したことがある学校で、その背景にやはり温暖化があることに気づかせる。
破局した未来という想定から現在を見直し、それによって、ふたたび未来の状態を実感する。まだ実際に災害に遭ってはいないのに、地球温暖化が進んだ未来の状態を実感できるようになる。これが地球温暖化を初等中等教育に取り入れる一つのあり方だろうと思う。
「海と希望の学校 in 三陸」
(北川貴士・東京大学大学院新領域創成科学研究科教授)
東京大学大気海洋研究所の大槌沿岸センターがある岩手県大槌町を始めとする三陸は、高齢化と過疎に悩まされている。さらに東日本大震災で壊滅的な打撃を受け、さらなる人口流出を招いた。
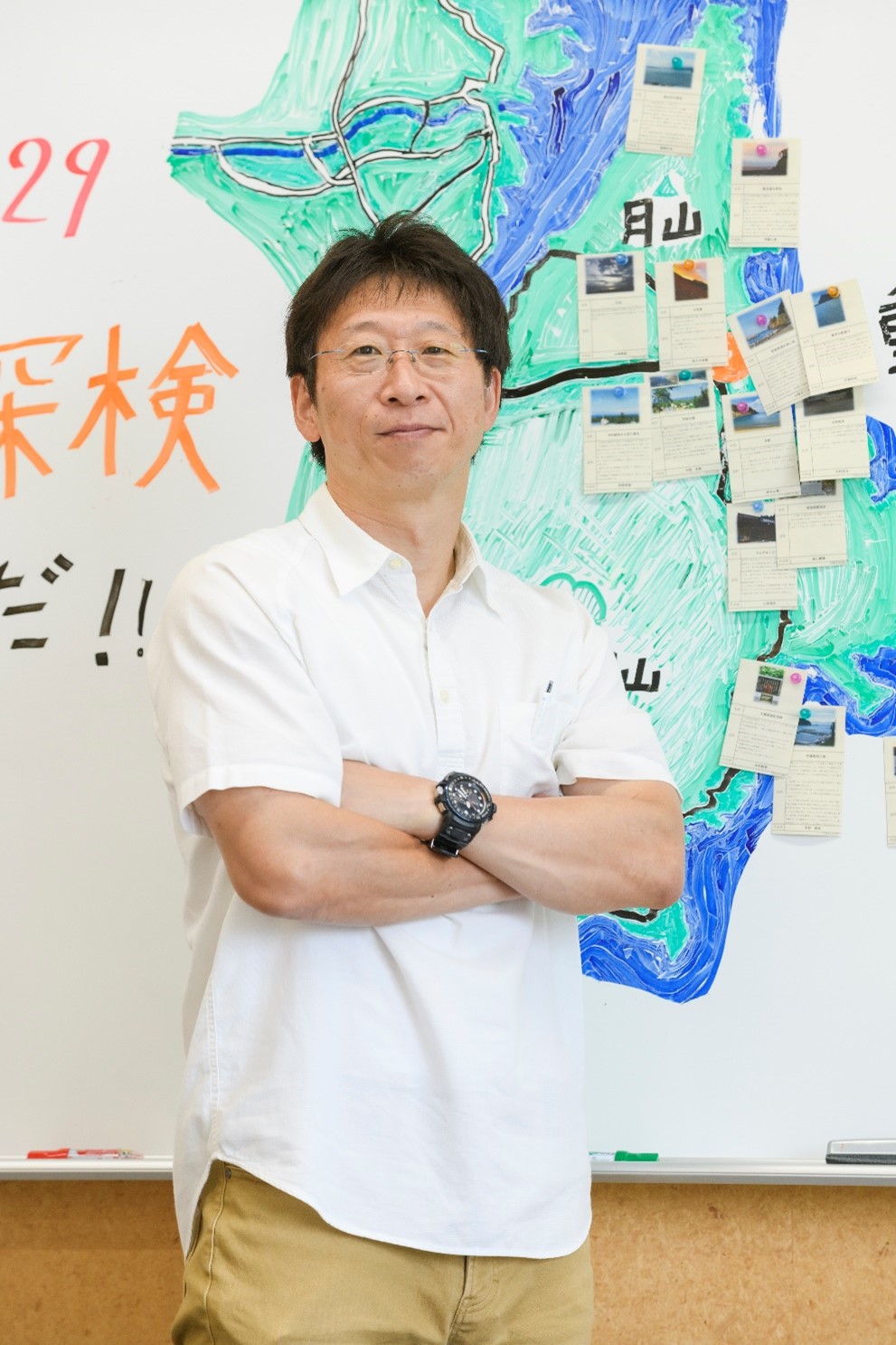
東日本大震災の直後から、東北マリンサイエンス拠点形成事業という震災復興に関する研究が始まった。しかし、こうした短期的な調査は、復興の先にある地域創成の支えには、かならずしもじゅうぶんになることができない。現実には、震災後、地域社会と海との間、次世代を生きる子どもたちと海との間に距離ができてしまっている。この溝を埋めることが私たちの使命だと思った。
そのころ、おなじ東京大学の社会科学研究所が提唱する「希望学」に出合った。大槌町の隣の釜石市では、製鉄会社の溶鉱炉の火が消えて、人々の元気がなくなっていた。社会科学研究所は、この釜石の人たちがどのようにして希望を見いだしているのかを調査した。そうして、地域の復興に欠かせない要因として「ローカル・アイデンティティー」の大切さを掲げている。
それを知った私たちは、三陸の海の地位の向上こそがローカル・アイデンティティーの再構築なのだと気づいた。そして、海のもつ可能性を生かし、地域の振興に貢献する人材を育てる「海と希望の学校 in 三陸」を社会科学研究所と2018年に始めた。
いま、釜石の会社がつくったサバの缶詰が売れている。これまでサバ缶といえば、水煮とみそ煮だった。サラダやパスタに使うイタリアン系はなかった。そういう使い方をする人がいるとすれば、それはきっと大人の女性だろう。それなら、もらってうれしいし、飾っておいてもかわいいサバ缶がいい。そいうラベルをつくろう……。
ここまでやると、もう物を売るのではなく、物語を売ることになっている。そうすると、少々高くても買ってくれる。そして、子どもたちが、それに気づく。学校では、サバ缶を題材にした探求的な学習を自発的に始める子がでてくる。
磯ラーメン実習というのもある。さまざまな海産物を持ち寄って、それを使ってラーメンをつくる。それを、他の地域の磯ラーメンと比べてみる。そうすることにより、自分たちのローカル・アイデンティティーを確認させる。
人材育成という観点からは、私たちの活動はさらにギアを上げる必要がある。次の世代を生きる子どもたちが地域に愛され、そこで希望をつなぐよう、研究者を含め海に関わる仕事になるための行動を起こさせたい。それが私たちとして地域貢献だろう。
あらためて気づいたのは、私たち自身が海の魅力を伝えることを楽しみ、その姿を子どもたちに見せることが大切だということ。子どもたち、「ああいうふうになりたい」と思ってもらうこと。これが根本にあるのだと思う。
「教養部全学ゼミ『海のアジア』」
(折山光俊・経済産業省貿易経済協力局経済協力研究官)
日本を含むアジア地域には、中東の石油や台湾海峡、重要な海上交通路である「シーレーン」など注目すべき事柄がある。通商産業省に入省して以来、アジアに関係する仕事をしてきた。その経験をもとに、おもに休みの日に半日かけてゼミを開講している。

日本で海といえば、海洋資源、交通路としての海だが、アジアは文化的にも共通するものを持っている。授業では、海をたんなる交通路などとしてだけではなく、文化的な面にも注意して見ていくようにしている。
たとえば紛争がおきたとき、それを武力によらずに解決する方法を考えるには、メディアの伝える情報だけではなく、実際の問題はどこにあるかを一次資料に基づいて正しく理解していかなければならない。それを授業で強調している。また、海外進出した企業が地元に与える影響、すなわち環境問題とか地域住民への配慮といったものも考えていきたい。
「海で学ぶ」
(早稲田卓爾・東京大学大学院創成科学研究科教授)
「海で学ぶ」は、海洋アライアンスが発足した翌年の2008年に、教養学部の1、2年生を対象として始めた全学体験ゼミナールだ。今年で15回目になる。

東京大学の大学院理学系研究科は、三浦半島の油壷に「三崎臨海実験所」という付属施設をもっている。「海で学ぶ」は、講義や実習を組み合わせてここで実施している。東大生というと、受験勉強ばかりしてきて、与えられた問題を解くしかできないのではないかと思うかもしれないが、さまざまな事に興味をもっている素晴らしい学生たちがたくさんいる。そうした学生が集まってお互いに刺激しあっている。
実験所には「櫓(ろ)」でこぐ「和船」がある。上手になると、あまり力もいらない。なぜそれで船が進むのか。これは、渦度の保存とか非定常流れといった流体力学の話になる。よく観察すると、うまくこげたときは、櫓のまわりに渦ができる。それが推進力のもとになるのではないかと思っていたら、和船に詳しい人が、やはり「きれいな渦を作るのが大切だ」と言っていた。
重要なのは、「学ぶ」「教える」より、むしろ好奇心だ。それをわかってくれる学生が多かったように思う。今後かれらがみんな海を専攻するわけではないだろうが、さまざまな分野を志す学生たちが「海」というキーワードのもとに集まる貴重な場になっている。
「研究・教育において現場や地域に行くこと関わること」
(安田仁奈・東京大学大学院農学生命科学研究科教授)
かつて宮崎大学に在籍していたころ、地域と大学、行政、民間がみんな一緒になって海の保全に取り組んでいた。大学の学生や教員、行政や漁協、ダイビングの関係者など、あらゆるステークホルダーが集まってサンゴ群集を保全しようとする組織を2011年に設立した。サンゴの調査や、サンゴを食べるオニヒトデの駆除、子ども向けの観察会などを実施してきた。

学生にとっても、アウトリーチや社会貢献に参加して得るものは多い。地域の関係者にはいろいろな立場の人がいることを学ぶことができる。自分が学んでいる海洋生物の話を一般の人にどう説明するか。説明して面白いと思ってもらうためには、自分がもっと勉強しなければいけないという自覚をもつようになる。
こうした活動では、地域の方々と信頼関係を築くことが重要だ。そのとき、「海」は結束を強めるキーワードになりうると実感している。これからの海の保全を考えるとき、子どもたちと一緒に活動することは、将来への大きな投資になる。
だが、こうした活動に参加する大学の教員は、大学での研究や教育とは別にボランティアで活動しているのが実態だ。そんなことに関わるより論文を書いていたほうが、研究界からははるかに高く評価される。したがって、地域のみなさんと共に進めるこのような活動に時間を割くには、それなりの覚悟が必要なのが現状だ。大学教員の業績を評価するシステムを見直していく必要を感じる。
学生を海の現場に連れていく活動を、いろいろ行ってきた。こうした体験をした学生たちは、卒業後にすごい力を発揮してくれる。そのまま研究者の道に進むとはかぎらないが、官庁や会社などさまざまな職業につき、環境問題の現場を知っているからこそ、そこから意見を言えるようになる。それがとても重要な点だ。
「水中ロボコン―水中ロボット競技会を通した学生教育―」
(巻俊宏・東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授)
水中ロボットの競技会を通した学生教育の取り組みについて紹介したい。「水中ロボネット」というNPO法人が主体となって活動しており、ここには東京大学のスタッフがたくさん関わっている。

水中ロボットは、人間が行くのは危険な過酷な水中で、人間に代わって資源の探査やインフラの点検などを行うロボットだ。このロボットを題材に、広い分野にまたがった教育ができる。ロボットなので、機械や電気、コンピューター関係ではソフトウエアの知識が必要だ。水中を動くので流体力学が関係するし、強い圧力にも耐えなければいけない。
チームワークも必要だ。みんなで計画を立て、失敗して反省して、最後にやっと成功する。その繰り返しだ。これは工学系のチャレンジでは非常に大切なことだ。
こうした活動を行うには、乗り越えるべき課題もある。ひとつには、やはり水中ロボットをつくるのは難しい。内部に水が漏れたら一瞬でダメになってしまうこともある。だから、初心者だけが集まっても、うまくいかない。経験豊かな指導者が必須だが、その数が限られている。また、ロボットを動かせる広いプールが必要だが、油漏れなどを心配してなかなか貸してもらえない。
こうしたなかで2013年に設立されたのが水中ロボネットだ。水中ロボット競技会や講習会を通し、次世代の水中ロボット工学、水中工学について研究開発、教育貢献することが目的だ。毎年開催している競技会には、学生のほか一般の方も参加できる。水中ロボットに興味をもつ人が自作のロボットを発表する。水中でロボットを動かす機会と楽しみを提供し、参加者どうしで情報や意見を交換してもらう。
こうした活動を続けてきて、水中ロボット関係の業界に就職する人がでるような効果も生まれてきている。企業のスポンサーも増えてきた。ただし、さきほども述べたが、指導者が足りない。私のような大学教員がボランティアで指導しているのが実態で、このままでは、これ以上、規模を大きくするのは難しいだろう。
「洋上風力をめぐる、地元社会の合意形成」
(山口健介・東京大学公共政策学連携研究部特任講師)
海洋学際教育プログラムの海洋問題演習という授業で2020年度以降、洋上風力発電事業における合意形成について、秋田県の一地域を定点観測してきた。

合意形成とは英語ではコンセンサス・ビルディング。ずべての利害関係者の利益に向け、全会一致の合意を求める誠意ある努力に関する過程のことだ。その背景には、多数決による決定に対して少数意見を尊重しようという精神がある。合意形成を通じた決定は、単純な多数決による決定より安定して効率的であることがたびたびある。
洋上風力には10年、30年といった長い事業期間が必要で、法的には三つのプロセスを踏むことになっている。まず、有望な区域に指定される。そして法定協議会で合意形成する。そして入札だ。法定協議会が合意形成の場なのだが、現実には、もうそこまで行ってしまうと、白紙に戻すことはできない。事実上、工程を決めて事業を推進する場になってしまっている。
そこに至る実際の「合意形成」にしても、たとえば漁協の組合員で中立の考え方だった人が、漁業補償を積まれて賛成に回る。そして合意が形成される。これがはたして、ほんとうの意味での合意形成といえるのか。
参考になる考え方が平和学にある。「積極的平和」とは、たんに戦争がない「消極的平和」の状態ではなく、不平等や格差といった不公正を暴力ととらえ、その暴力もない状態をいう。補償で賛成に回ることへの違和感は、これが「消極的な合意形成」である点にあるのではないか。
では洋上風力発電事業の「積極的な合意形成」とはなにか。それを考える鍵は、さまざまな利害関係者の「長期的ビジョンの共有」にあると思う。
だが、地方と都市との関係ひとつみても、風力発電の風車から発生する低周波振動による健康被害、景観への悪影響といったリスクを背負うのは地方で、そこから生まれる電気を使うのは都市。こうしたなかで長期的ビジョンを描けといっても、簡単ではないかもしれない。
しかし、洋上風力発電は長いあいだ続く事業なので、はたして消極的な合意形成でよいのだろうか。積極的な合意形成に向けて私たちができることはなにかを考えていきたい。
「カーボンニュートラル社会実現に向けた海藻藻場の役割と可能性:大学院生の視点から」
(羽根由里奈・東京大学大学院農学生命科学研究科特任助教)
日本は、2050年度までにカーボンニュートラルを実現するという目標を掲げている。二酸化炭素の排出削減努力だけでは、この目標を達成することは難しく、いま「ブルーカーボン」が注目されている。

ブルーカーボンは、海洋生物に取り込まれ、海底に堆積した炭素を指す。この炭素は数百年から数千年にわたって貯留されると報告されており、二酸化炭素を当分のあいだ除去しておけることになる。海洋生態系のうち、海藻や海草、マングローブ林などが大きな役割りを果たす。
海洋学際教育プログラムの「海洋問題演習」では、大学院生たちがブルーカーボンを取り巻く問題やその解決策を考え、社会提言にまとめた。ここでは二つの提言を紹介したい。
一つは、洋上風力発電の施設を海藻の養殖場として利用するというアイデアだ。日本の北部、南部にそれぞれ適した海藻を用いた養殖システムを考えた。2050年度までに90ギガワットの洋上風力施設が導入されると仮定すると、海藻を養殖する「藻場」の面積は最大62万ヘクタールとなることが見込まれる。こうした数字をもとに試算すると、北部エリアでは年間に最大600万トンの二酸化炭素を吸収できる。南部エリアでも700万トンになった。これをもとに関係者にインタビューしたり現地調査したりして、それぞれのエリアで最適と思われる海藻養殖システムを考案した。
もう一つは、ブルーカーボンクレジット制度の普及に向けた課題の整理と解決策の提示がテーマだ。国内では「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合」という団体がこの制度を運営している。組合に認証されている団体、されていない団体、認証申請したことのない団体にアンケートを実施し、クレジットの申請から認証に至るまでの過程を、ブルーカーボンを「作る」「測る」「売る」の三つのフェーズに分けて考えた。これをもとに、申請しようとする団体が、それぞれのフェーズでどれくらいのレベルに達しているかを自ら数値的に評価できるような指標をつくった。
「海洋学際教育プログラムの15年」
(山本光夫・東京大学大学院農学生命科学研究科教授)
「海洋学際教育プログラム」は、東京大学の横断型研究プログラムとして2009年度に開始された。海洋に関わる国際的な人材の育成を目指し、海で現実に起きている社会問題の解決に資するべく、分野横断型、文理融合型の教育を行っている。2022年度末までに約200人がプログラムを修了している。

特徴的なのが「海洋問題演習」という授業だ。前期はおもに実務経験者による事例紹介の講義で、後期は、いま社会で起きている現実の課題を選び、その解決へ向けた提言を学生がグループワークでまとめて社会に発信する。受講した学生にアンケートすると、他分野の学生とのグループワークを通して学際的な議論ができたことを、もっとも良かった点として挙げている。異分野の協力で問題を解決することの難しさや重要性を、学生たちは身をもって知ってくれたと思う。
もう一つの特徴が、国内外のインターンシップ制度だろう。国内では国土交通省の本省や気象庁、海上保安庁などに、独自に年10人ほどの枠を提供していただいている。
海外インターンシップでは、数か月から6か月にわたり、国連などの国際機関や研究機関に学生を派遣し、最前線の専門家や研究者との議論を、実際の世界の舞台で体験してもらっている。東京大学にも将来、こうした場で働きたいと考える学生がいて、そのためのキャリアパス形成に役立っている。
プログラムの修了生は、省庁や一般企業など幅広い分野に就職している。修了生たちのネットワークを充実させることは、海洋に関わる重要な課題について、海洋アライアンスのシンクタンク機能を強化することにもつながると思う。
「求められる海洋人材:第4期海洋基本計画における取組
(諏訪達郎・内閣府総合海洋政策推進事務局海洋政策調整官)
「現在の海洋基本法では、基本的な施策の一つとして、海洋に関係する課題に的確に応じるために必要な知識や能力をもつ人材の育成を挙げている。

この法律に基づいて今年4月に決まった第4期海洋基本計画では、「総合的な海洋の安全保障」と「持続可能な海洋の構築」が二本柱になっている。それに加えて、着実に進めるべき主要な施策として、海洋人材の育成と確保、国民の理解増進も掲げられている。
日本では少子高齢化によりそもそも人口が減っているうえ、産業構造の変化や技術革新に対応できる人材の必要性が高まっている。第4期海洋基本計画では、第3期に比べてそういう問題意識が強く出ている。
産業構造についていえば、たとえば洋上風力発電のように発展が見込まれている産業の担い手をどう育成していくか。DX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組んでいける人材の育成も必要になってくる。数値的なシミュレーション技術も必要だ。データサイエンティストなど他分野の人材が海洋分野に参入する必要もある。また、海洋に関連する国際法の専門家の育成も、新たな問題意識からその必要性が挙げられたものだ。
これからも、産業界などの議論も踏まえて、次の第5期の計画につなげていきたい。
「日本において海洋の産官学連携はなぜ活性化しないの?」
(山口功・日本電気ANSビジネスプランニング統括部上席技師)
航空宇宙防衛を担当する部門で働いてきた。防衛関係でみると、欧米は産官学の連携がとてもうまくいっているが、日本はうまくいっていない。マクロ的な視点でみると、産業が育っていない。とくに海の世界はそうだ。

大学や独立法人などが活動するさまざまな局面に国などの資金が投入されているが、これはおもに先端分野やスタートアップが対象で、大規模な産業化とのあいだに隔たりがある。「死の谷」だ。そのために、スタートアップ企業と既存の企業との連携がなかなかうまくいかない。
日本の企業は、新しいこと、先の見えないものに投資しづらい。新たな技術が開発されてある程度のところまで行っても、この「死の谷」を越えられずに事業機会を失っているのではないか。たとえば米国には、先端技術に対して、多少の失敗はあってもそれにお金を短期間でつぎこんで、どんどん先に進む企業がある。
事業というものは、まず先端技術が生まれ、それが育つ成長期をできるだけ長く継続して、そこでお金をもうける。やがて時代に合わなくなって衰退する。海洋分野には、こうした産業の育成という見方が足りないのではないか。たとえば海洋研究開発機構は学術研究と技術開発が主で、産業の育成という観点が欠けている。企業の側も、たとえば白物家電が厳しくなっている現在、その人的リソースを移動させるのではなく、その部門を売却するようなことをしてしまう。
スタートアップで生まれた技術をポンと持ってきてもだめだ。どこかの国の企業がそれを事業化してドーンと持ってくると、日本の企業は手も足も出なくなってしまう。たとえば物流のアマゾンは、衛星による通信事業に参入している。物流から通信からすべてを押さえ込もうとしている。そうしたなかで、日本のメガキャリアは生き残れるのだろうか。新しい技術から製品にいたるさまざまな領域について、その隠れた共通性や関連性を見つけ、点を線で結ぶことが必要だ。そのあたりが日本人には足りない。
東京大学の「海」を担う次世代のみなさんには、先端的な技術の研究はこれまでどおりガンガン進め、それを事業として興すところまで担ってほしいと思う。
「文理融合とはいうものの……」
(保坂直紀・東京大学大学院新領域創成科学研究科特任教授)
海が抱えてる社会問題を解決しようとすると、狭い専門領域に閉じこもっていては前に進めない。分野を超えた問題ばかりなので、私たちが東京大学で提供する海洋学際教育プログラムも、分野横断型、文理融合型の教育を目指している。

だが、この文理融合というのは、ことのほか難しい。いまの日本で感染症についてなにか方針を決めなければいけないとする。すると、なんとか委員会などというものが立ち上がって、医学や経済学など異分野の専門家がメンバーになる。だがこれは「文理集合」であって「文理融合」ではない。特定の事柄に関してはその分野の専門家が発言し、それを他の人たちは黙って聞くだけだ。自分の専門ではないから発言しないのだ。つまり「議論」がない。
専門家が自分の詳しい分野について見解を述べ、たくさんの「専門的な見解」が議事録に残る。そのなかから政府が自分に都合のよい発言をつまみ食いし、専門家の見解を政策の決定に生かしたと主張する。
たとえば3人が集まったとして、議論がなければ、知恵の総和は3人分にしかならない。たんなる足し算を超えて3人の和より優れた知恵を生み出すのが議論ではないか。異分野の人とでも深くて優れた議論のできる人材が必要だ。
そのために大学がやらなければならないのは、たんに専門家を育てるのではなく、異分野の人と議論するための共通の土俵になる、自分の分野にとらわれない論理的な思考力をはぐくむこと。読み書きそろばんと論理的思考力で高度な議論の土俵に参入できる人材を育てることだ。
大学の研究者は、自分の専門分野の論文を書くことで評価を得る旧来の「論文第一主義」から逃れられていない。さきほどの安田仁奈さんのお話にもあったとおりだ。異分野に関心をもてば、いまの日本では損をする。研究者に対するそうした大学や学術界の評価システムを変えていくことも必要だろう。
※シンポジウムの要旨集はこちらです。
文責:サイエンスライター・東京大学特任教授 保坂直紀