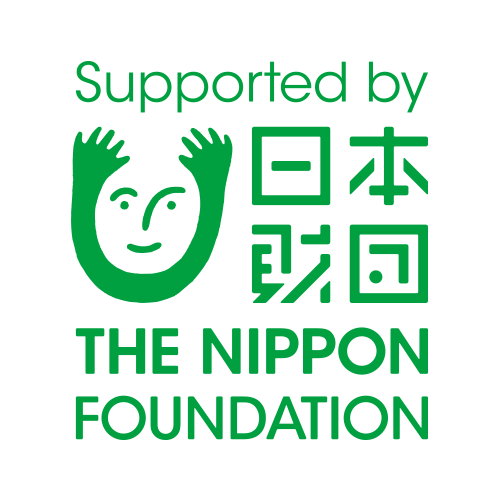TOPICS on the Ocean
【シンポジウム】「第15回東京大学の海研究:海洋プラスチック研究のゆくえ」(2020/10/15)【動画があります】
東京大学海洋アライアンス連携研究機構の第15回「東京大学の海研究」シンポジウムが10月15日、開かれた。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、オンラインでの開催となった。今回のテーマは「海洋プラスチック研究のゆくえ」。レジ袋の有料義務化などで関心が高まっているプラスチックごみに関する研究の現状を、東京大学の教員8人が紹介した。参加者は約550人で、キャンパス構内のホールで開催してきた例年を大きく上回った。

第15回東京大学の海研究の全体の流れ
プラスチックは20世紀後半から、わたしたちの生活を支える素材として急速に広まった。1950~2015年に生産されたプラスチックは83億トン、年に480万~1270万トンがごみとして海に流れ込むと推定されている。2018年にカナダで開かれた主要国首脳会議(G7)では、「海洋プラスチック憲章」をカナダと欧州諸国が承認し、各国がプラスチックごみの削減に取り組むことを公約した。日本でも、スーパーやコンビニエンスストアなどで無料配布することが多かったレジ袋が、2020年7月から原則として有料化された。プラスチック製のレジ袋を有料化することで、プラスチックごみの削減を社会に意識づけるのが狙いだ。
東京大学は、日本財団から研究費を受け、「東京大学FSI-日本財団海洋プラスチックごみ問題に対する科学的知見充実化プロジェクト」を、2019年度から3年計画で実施している。今回のシンポジウムでは、このプロジェクトに参加している研究者らが、海洋のプラスチックごみに関する研究の現状と将来への展望を解説した。
「東京大学FSI-日本財団プロジェクトの概要」
(道田豊・東京大学教授)
海洋に流れ込むプラスチックごみについては、2015年にドイツ・エルマウで開かれた主要国首脳会議(G7)以来、国際的な問題になっている。海に入るプラスチックごみの量は生産量の数パーセントにすぎないが、いちど海に出てしまうと、事実上、回収できない。そこが大きな問題だ。小さく砕けたプラスチックの細片は、生体への影響も心配されている。海に流れ込むプラスチックごみは東南アジアの国々で多い。日本は30位とされているが、それでも年間数万トンは出ているので、手をこまねいているわけにはいかない。
そこで、日本財団の支援を受けて始めたのが、2019年度から3年間の「東京大学FSI-日本財団海洋プラスチックごみ問題に対する科学的知見充実化プロジェクト」だ。
プロジェクトは、大きく二つに分かれている。一つは「研究」だ。大きさが5ミリメートルより小さい「マイクロプラスチック」のうち、とくに実態がよくわかっていない1ミリメートル以下の細片についての研究、そして生体が取り込んだ際の影響に関する研究。これらが解明されるには時間がかかるが、それまで座視しているわけにはいかないので、ごみがどの段階でどのように発生するのかといった、ごみの削減方策に役立つ社会科学的な研究も進めていく。もう一つが、研究成果を発信し、このシンポジウムのような場で、さまざまな方と議論を深めていくことだ。こうした過程を経て、もっとも効果的なごみの削減方策を提言できればよいと思っている。
国連は2021年から「国連海洋科学の10年」をスタートさせる。海洋が抱える問題を科学で解決するこの取り組みの中には、もちろん海洋プラスチックごみも入っている。ぜひこの「国連海洋科学の10年」にも貢献したい。
「海洋マイクロプラスチックの実態解明」
(津田敦・東京大学教授)
海のマイクロプラスチックは、どこから来て、どこへ行くのか。その実態の解明に、わたしたちのグループは取り組んでいる。プラスチックごみは、海岸で波にもまれて小さくなることもあるだろうし、外洋でも、太陽の紫外線や波で小さくなると考えられている。こうして小さくなったプラスチックごみの一部は、海の深いところへ沈んでいくようだ。
こうした事柄を考える際に重要なのは「サイズ(大きさ)」だ。一般的に言って、海の中にあるものは、生き物であれ、小さな粒子のような非生物であれ、サイズが小さいものは多く、大きなものは少ない。プラスチックごみにもこれが当てはまるとすると、じつは、大きさが5ミリメートル以下のマイクロプラスチックは予想より数が少ない。
海洋の小さな粒子を沈みやすくする仕組みとして、二つのことが考えられる。一つは動物プランクトンによる「捕食」。動物プランクトンの糞(ふん)には、たくさんの小さな植物プランクトンが含まれている。植物プランクトンは、そのままではほとんど沈まないが、糞になると1日に10メートルとか数百メートルとか沈むようになる。もう一つは「凝集」。珪藻(けいそう)という種類のプランクトンの殻のような重いものが、小さな粒子を絡めとりながら沈んでいく。マイクロプラスチックのような小さな粒子は、こうした仕組みで海底に沈んでいく可能性がある。
では、沈みにくい大きなマイクロプラスチックと沈みやすい小さいサイズの境目はどこかというと、おそらく0.01~0.1ミリメートルのあたりだろうと考えている。なぜなら、これが動物プランクトンに「捕食」される植物プランクトンのサイズだからだ。海面に長く漂うプラスチックごみと、海に沈んでいくものとの「運命の差」は、これくらいのサイズにあるのではないか。
このほか、過去70年にわたる海洋プラスチックごみの変化を調べたり、プラスチックごみを捕集できる簡便な装置で専門家以外の方にもデータの収集を手伝ってもらう仕組みを作ったりして、海洋のマイクロプラスチックの実態を、できるかぎり正確に把握したい。
「保管サンプル再解析による時空間分布変動の把握」
(高橋一生・東京大学教授)
これまでの研究によると、海に流れ出て浮遊しているはずのプラスチックごみのうち90%以上が行方不明になっている。つまり、わたしたちは、浮遊しているプラスチックごみのことが、よくわかっていない。プラスチックごみがこの先どう海に広がり、沈んでいくのかを考えるには、まず、いま浮遊しているプラスチックごみの実態を正確に把握することが必要だ。
しかし、浮遊しているプラスチックごみの観測には空白海域も多々ある。海洋プラスチックごみが注目されるようになったのはごく最近なので、そのための観測は数が少ないからだ。
そこで、わたしたちのグループが着目したのは、水産研究教育機構が実施している「サンマ資源量直接推定調査」だ。この調査では、虫捕り網のような「ニューストンネット」で、海面近くを浮遊するサンマの卵や稚魚を採取する。その際に網に入っていたプラスチックごみを使って、ごみの分布を推定してみた。この調査は、日本のすぐ東側から日付変更線を越えた海域まで東西を帯状に対象とするので、中緯度太平洋を広くカバーするこができる。
2016年の調査を使って調べたところ、日本近海や西経165度付近などに、マイクロプラスチックの密度が高い海域があった。1980年代後半に行われた観測に比べ、この30年あまりで約10倍に増えていた。
プラスチックの種類でみると、半分がポリエチレン、35%がポリプロピレンで、この割合はどの海域でもあまり変わらなかった。一方、発泡スチロールの素材であるポリスチレンは、東に行くほど減っていった。ポリスチレンはもともと海水より重いので、黒潮から続く東向きの流れに乗って日本付近から遠ざかっていくあいだに発泡スチロールから空気が抜け、沈んでしまうと考えられる。
サンマを対象としたこの調査で集めた試料は、1949年から保存されている。これからきちんと分析しなければはっきりしないが、プラスチックごみのようなものも含まれているようだ。いつごろから海はマイクロプラスチックで汚れていたのかも明らかにしたい。
「マイクロプラスチックの生体影響」
(酒井康行・東京大学教授)
わたしたち人間の排せつ物からは、10グラムあたり20個、大きさにして0.05~0.5ミリメートルのマイクロプラスチックが検出されている。非常に小さなプラスチック細片については、肝臓や腎臓などにも広まることが、ラットやマウスを使った実験で報告されている。世界保健機関(WHO)は、0.15ミリメートル以上のプラスチックは、排せつされて、人体内部に入ることはないとみているが、それより小さなプラスチックを対象にした研究は、まだあまり進んでいないのが現状だ。
わたしたちが知りたいのは、ヒトへの影響だ。そのための方法として、ヒトの組織を何種類か培養して実験を行い、それらの結果を数学的に統合してヒトへの影響を探ろうとしている。動物実験を介さないで人体への影響を直接的に調べていく方法だ。
小腸の培養組織を使った結果を紹介したい。実験では、「小」「中」「大」の3種類の大きさのポリスチレンを使った。大きさはそれぞれ0.00005ミリメートル、0.0001ミリメートル、0.0005ミリメートルだ。「小」と「中」は、栄養を吸収する上皮細胞を通って血管に入った。これが血液で運ばれて、いろいろな臓器に達すると考えられる。
「大」は、体内に取り込まれる仕組みが違っていた。腸壁にある「パイエル板」とよばれる部分から、血管ではなくリンパ管に入っていた。リンパ管経由で各臓器に広がっている可能性がある。小腸から取り込まれたマイクロプラスチックがリンパ管を通ってリンパ節に達したとき、そこにあるまざまな免疫系の細胞がどう反応するのか。それを確かめることが重要だ。
動物実験に代わり、このようにヒトの培養組織を使ってヒトへの影響を直接的に評価しようというのが、現在の世界的な研究の流れだ。大きめのプラスチック粒子が、血管ではなくリンパ管に入ることがわかったので、こんどはリンパ管について実験できる組織を培養し、免疫細胞への影響も調べていきたい。
「海洋プラスチックごみの削減方策に関する研究」
(高村ゆかり・東京大学教授)
海洋プラスチックごみの削減に向けた国際的な枠組みのありかたについてお話ししたい。
こうした枠組みは、すでにいろいろある。国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」には、海洋汚染の防止と大幅な削減が、2025年という期限つきで書かれている。国連海洋法条約にはプラスチックごみは明示されていないが、海洋汚染の防止を目的とするロンドン条約では、これを明確に対象としている。
ただし、ロンドン条約が規制しているのは意図的な投棄で、陸域からの流れ込みは対象にならない。国境を越えた有害廃棄物の移動を制限するバーゼル条約は、2019年に付属書を改正し、プラスチック廃棄物を明確な規制対象とした。このほか、国際条約とは違って拘束力のない国際プログラムもある。
国際的な枠組みをつくる際、それに法的拘束力をもたせるかどうかが大きな論点になる。拘束力をもって各国に義務を課そうとすると、それを嫌がる国はこの条約に参加しないことになり、国際的な効力がかえって及ばなくなってしまう。気候変動への取り組みで米国が「パリ協定」から脱退したのが、その例だ。拘束力のある条約が効果的だとはかぎらない。
より高い水準で条約を結ぶためには、科学的な知見が大切だ。明確な知見が示されると、それが国際条約を結ぶ動機づけになる。また、プラスチックごみに関しては途上国における対策が重要で、それを支援するための仕組みが必要だろう。
海洋プラスチックごみの管理を有効に進めるための国際枠組みとしては、科学的知見の進化にともなって合意が積み上がっていくような柔軟な制度を目指すのがよいだろう。いちど制度が合意されて終わりではなく、科学的な知見の強化についてまず合意し、それをもとに国家の規制措置をさらに合意していく形が現実的だ。
最近の環境政策は、国家だけでなく民間を巻き込むように変わってきている。気候変動対策がその例だ。企業がこの問題を経営にきちんと取り込んでいるかを情報開示し、投資家や金融機関がその企業に対する評価に使う。個人投資家は、循環経済や地域開発、気候変動と並んで、プラスチックの削減にも高い関心を示している。こうした国家以外の取り組みを促進する国際制度をつくり、対策の実効性を高めていくことも今後の課題だ。
「生分解性プラスチックの動向」
(岩田忠久・東京大学教授)
使用中は普通のプラスチックとおなじように使えて、それがごみとして環境中に流出してしまったとき、微生物がだす分解酵素で低分子化して、最終的には水と二酸化炭素にまで分解される。それが「生分解性プラスチック」だ。
生分解性プラスチックは実用化されているが、分解しやすい環境と分解しない環境がある。たとえば、すでに食品包装などに使われている「ポリ乳酸」。分解されるには温度が60度以上、湿度も60%以上が必要で、そのへんの土や川、海の中では分解されない。使えるのは、たい肥(コンポスト)をつくるような高温多湿の環境のみだ。
生分解性プラスチックは、その用途により、普通のプラスチックとして使いたい期間、つまり分解が始まるまでの時間が違う。農業で使うフィルム状のシートなら、土にすきこんで1週間くらいで分解してほしいし、砂漠の緑化に保水材として使うなら、埋めて1年くらいは長持ちしてほしい。わたしの研究室では、プラスチックに分解酵素を埋め込んだ。プラスチックが劣化して亀裂が入り、そこに水がしみこむと、酵素が働いて分解が始まるプラスチックだ。分解開始までの時間を制御する試みだ。劣化して砕け、小さくなればなるほど、分解は速くなっていく。
さらに、いったん分解が始まった生分解性プラスチックの分解スピードをコントロールする方法も研究している。プラスチックに含まれる「結晶」の量や分子の形を変えると、このスピードを変えられることがわかった。このようにして、分解の開始時点、そして分解開始後の分解スピードをコントロールできるようになれば、生分解性プラスチックは、実際に使える材料として世の中に出ていくことができるだろう。
衣服に使われるポリエステルは、ペットボトルの原料であるポリエチレンテレフタレートの繊維のことだ。洗濯をすると多量の繊維状ポリエステルがマイクロプラスチックとなって環境中に出ていく。細かい研磨材として使われるプラスチックもある。なんでも生分解性プラスチックに置き替えるのではなく、このように、いったん環境中に出たら回収できなくなってしまうプラスチックにこそ、生分解性の素材を適用していくことが大切だ。
「UNIDOとの共同プロジェクトの現状」
(山本光夫・東京大学准教授)
海洋プラスチックごみの削減に向けて、農業廃棄物を有効に活用することを目的に、国連工業開発機構(UNIDO)との共同プロジェクトをエジプトで進めている。
エジプトで多く発生する農業廃棄物には、麦わら、トウモロコシの茎、稲わら、サトウキビバガス(サトウキビのしぼりかす)などがある。ナイル川上流の流域に多いのはバガスだ。
この地域では、バガスを原料とした紙の製造がすでに行われている。麦わらや稲わらを使おうとすると、農地に放置してあるものをあらためて回収し運搬してくるコストがかかるが、バガスなら、サトウキビを使った製糖工場でまとめて廃棄されるので、輸送コストも低く抑えられる。バガスには50%くらいのセルロースが含まれており、すでにバガスを原料とした新聞紙や印刷用紙が製造されていることも考え合わせると、プラスチックを代替する紙製品の原料として、バガスは有力な候補となりうる。
現在、バガスはおもに燃やしてエネルギーとして利用されている。カイロ大学の研究者や専門家などにインタビューしたところ、紙を製造するよりエネルギー利用のほうがコスト面で有利だという。また、既存の製紙工場ではおもに印刷用紙をつくっているため、プラスチック容器の代替品を製造するのは現状では難しい。バガスはプラスチックを代替する紙の原料として有望ではあるが、こうした現状を踏まえた具体的な提案が必要になってくるだろう。
「海洋学際教育プログラムの成果報告」
(保坂直紀・東京大学特任教授)
海洋アライアンスは、東京大学の大学院生を対象に、海に関する事柄を文理横断的に学ばせる「海洋学際教育プログラム」を日本財団の支援で実施している。このなかの「海洋問題演習」は、海洋が抱える社会的な課題について、その解決に向けた提言をグループワークでまとめる科目だ。海洋のプラスチックごみは2019、2020年度のテーマになっている。2019年度の2グループがまとめた提言を紹介したい。
【海洋プラスチックごみ問題を解決するための新ラベルの提言】
消費者が当事者意識をもって海洋プラスチックごみ対策に取り組む社会を目指し、「プラマイ0(ゼロ)ラベル」と「プラ0ラベル」を提言したい。
「プラマイ0ラベル」は、プラスチックを使用している製品に表示し、製品にはプラスチックの回収処理費用として数円を上乗せする。消費者にプラスチック製品を使っている意識をもたせ、それが適切な回収と処理に責任をもつ製品でもあることを示す。ペットボトル1本につき5円を上乗せすれば、プラスチックごみを適切に焼却できる処理施設を年間で10炉ほど建設できる試算になる。消費者は、価格が多少高くても「こだわりのある商品」なら買うという調査結果もある。
「プラ0ラベル」は、プラスチックを使っていない製品であることを付加価値としてアピールする。このラベルを、むかしから学校を通してなじみ深い「ベルマーク」のように、企業からの協賛で運用することができれば、企業の社会貢献活動としても有益だろう。学校にとっては、環境問題に対する実地教育ともなる。こうして、プラスチック製品の使用を減らし、プラスチックごみの削減につなげていく。
【海洋ゴミ市民活動へ】
フィールド調査で沖縄に行き、県の担当者から「海をプラスチックごみからギリギリ守っているのは市民ボランティアの活動」という話を聞いた。市民参加の意義は大きい。そこで、いま85%の人が利用しているとされるスマートフォンの活用を考えた。
「ゲーミフィケーション」という考え方を使ったアプリを提案したい。ゲーミフィケーションとは、ゲームがもつ「ユーザーを楽しませる仕組み」をゲーム以外で活用すること。「明確な目標」「課題とその報酬」「ユーザー間の交流」「現状の可視化」がポイントだ。
たとえば、海洋ごみで凶悪化した生物を倒す対戦型ゲームを想定しよう。ここに、海ごみ問題の解決という目標が明確に提示されている。海岸のごみ清掃に参加することなどで、戦うための自分の戦力がアップする。報酬の獲得である。活動の成果をランキングで示したり、ユーザ―同士が対戦、協力できる局面をつくったりすることで、ユーザー間の交流を促す。ごみ清掃した海岸の写真を投稿すれば、ごみ汚染の現状を知ることができる。
こうしたゲームのアプリをだれがつくり、運営していくのかといった課題は残ったが、ゲーミフィケーションの発想を使えば、ゲーム好きの個人、漁業関係者、市民団体、自治体関係者、研究者など、社会の広いメンバーが海の環境を守る目的でつながることができるのではないか。
「研究の方向性に関する議論」
(モデレーター保坂直紀・東京大学特任教授)
――国際的な枠組みをつくる際に、科学的な知見はどのような意味をもっているのだろうか。
【高村】たとえば気候変動の問題に関しては、ここ数十年の研究の蓄積があり、政策決定の際に依拠できる「証拠」がかなり出てきている。プラスチックごみについては、まだそこまで到達できていないが、気候変動と同様に、科学的な知見を集積して政策側と確かな情報を交換しながら、国際的な枠組みをつくっていくことが必要だろう。
――海洋のプラスチックごみについては、2025年とか2030年というように目前の期限つきで実行の目標が示されている。科学研究は、それまでに間に合うのだろうか。
【高村】実現できそうな簡単な目標ではなく野心的なゴールを定めることで、技術的な課題、社会システムの課題を洗い出す。こうした期限目標は、そのような意味をもっている。
――社会と科学の関係について、ほかに気づくことはないか。
【道田】プラスチックごみが私たちに与えるリスクについては、研究が進めばだんだん正確にわかっていくのだろうが、それでもある程度の幅は残る。この「幅」についての解釈が、受け止める社会の側でまちまちだ。科学の側が結果を示す際の問題なのか、受け止める側の問題なのか、あるいはその両方なのか、それはよくわからないが。この受け止め方に違いがあると、そこから得られる政策が別の方向に行ってしまう可能性がある。このさき10年くらいの期間を考えると、この受け止め方の違いをどう縮めていくのかが課題だろう。
【津田】オゾン層の破壊が発見されてフロンの国際的な規制につながったように、科学の知見がダイレクトに環境の保全に生かされればよいが、これはなかなか難しいのではないか。科学者と個々の市民、あるいは行政だけでは社会は動かない。大切なのは、意思決定する市民や行政を科学と結びつける、マスメディアや市民団体などの「中間層」だろう。その役割が、日本ではまだ弱いような気がする。
――リサイクルに関する話が少なかったという参加者からのご指摘がある。
【道田】今回はお話しできなかったが、私たちの「東大FSI-日本財団プロジェクト」では、リサイクルを始めとするごみの流れに関する研究テーマに、京都大学の専門家にも加わってもらっている。ここで研究を進めているところだ。
【山本】さきほど農業廃棄物を有効活用するエジプトとの共同研究についてお話しした。とくに稲わらなどは、ただ燃やされて二酸化炭素の排出源になってしまう。これらをプラスチック製品の代替品をつくる原料として利用できれば、リサイクルの観点から環境の保全に貢献できることになる。
――プラスチックごみ問題の解決と気候変動の問題とでは、どちらが難しいか。
【高村】プラスチックごみ問題の解決は、技術的にもまだ先が見通せない。その点に現段階での難しさがある。それに、プラスチックといっても、さまざまな用途がある。それをひとくくりにして議論することの妥当性も問われる。プラスチックも、用途によって、削減する、少し削減する、リサイクルするといった、さまざまな選択肢があるだろう。それぞれにどの選択肢を選ぶと人の行動を変えることができるのかを考えることで、対応の道が開けてくるのではないか。
※シンポジウムの要旨集はこちらです。
文責:サイエンスライター・東京大学特任教授 保坂直紀