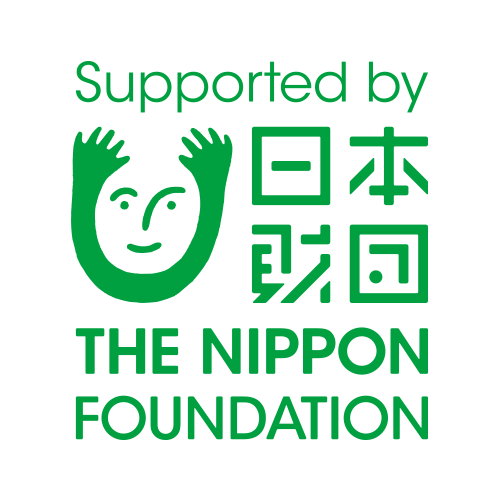TOPICS on the Ocean
海洋アライアンスのシンポジウムで魚食の未来を議論(2019/10/31)
東京大学海洋アライアンスの第14回「東京大学の海研究」シンポジウムが10月31日、東京都文京区の東京大学農学部弥生講堂で開かれた。テーマは「水産改革と日本の魚食の未来」。改正されたばかりの漁業法と日本の水産の将来について、専門分野の違う5人の研究者ら約130人の参加者がともに考えた。
日本ではだれがどのように漁をするのか――。この水産業の基本を定めた漁業法が、2018年12月に改正された。シンポジウムを企画した東京大学大学院農学生命科学研究科の八木信行教授によると、1949年の漁業法成立から70年ぶりの大幅な改正だ。日本の伝統的な漁業管理は、漁船や漁具のサイズなどの「漁獲能力」、漁業を行う「人間組織」、沿岸生態系などの「漁場環境」を中心に行われてきた。今回の改正は、「魚の資源量」の科学的な推定を管理に取り入れる欧米型の流れに沿っており、その点で賛否があるという。
改正された漁業法は、具体的な運用の基準などを整備して2年以内に施行される。いまその実効性が問われる局面にある。シンポジウムでは、従来型の漁業管理、資源量にもとづく科学的な管理、国による環境管理の留意点などのさまざまな観点から、今後の水産業が解決すべき課題を提起した。
なお、詳細は各講演者ごとに動画で紹介しています。
「日本の漁業管理のあり方:オストロムの設計原理の視点から」
(石原広恵・東京大学助教)
東京大学大学院農学生命科学研究科の石原広恵助教は、漁業資源を、他人も利用できるが、それが自分の利用に影響を及ぼす「共有資源」ととらえ、その管理について述べた。
魚や田んぼの水のような共有資源は、だれかが取ったり使ったりすると減る。放っておくと「早いもの勝ち」の心理がはたらき、魚なら最後の一匹まで取りつくすことになる。そのため、資源を持続的に使うには、なんらからのルールが必要だ。
石原さんは、共有資源の自主管理に関する研究についての第一人者で、ノーベル経済学賞を受賞したエノリア・オストロム氏の考え方を紹介した。 オストロム氏は、共有資源の「早いもの勝ち」を避ける制度を設計するための8つの原理を示した。
・明確に定義された境界線が存在すること
・費用に利益が見合っていること
・多くの利用者の意見が意思決定に反映されること
・利用状況や利用者の動向が監視されていること
・ルール違反の処罰の重さは事柄の軽重によること
・争いを解決するしくみが備わっていること
・制度設計する利用者の権利が外部から脅かされないこと
・管理する団体がさまざまなレベルに存在すること
三重県志摩市和具地区のイセエビ漁では、漁業協同組合(漁協)によるこの「オストロム型」の管理が有効に機能している。欧米型の科学的な量的管理も重要だが、日本の伝統的な沿岸漁業の場合は、地域社会の特徴などに重きをおくオストロム型の管理を再評価する必要もあるのではないかと、石原さんはいう。
「ゴードン型管理と日本漁業」
(山川卓・東京大学准教授)
東京大学大学院農学生命科学研究科の山川卓准教授は、取ってよい魚の量を決めるために科学的な手法を使う「ゴードン型管理」の考え方を紹介した。
もし親の魚がまったくいなければ、時間がたってもその魚は増えない。もし、その場の環境が許す最大量の魚がそこにいれば、時間がたっても、やはり魚の量は増えない。そのどこか中間に、魚がもっとも増えやすい量があるはずだ。これを「最大持続生産量」という。
資源量を科学的に推定するには、さまざまな影響を受けながら変化する魚の量を、こうした単純な「モデル」に置き換える。これをもとに取るべき魚の量を決め、その目標に合うように管理し、その結果を評価して必要に応じて次の管理戦略の立案に生かす。ビジネスの世界で使われる「計画」「実行」「評価」「改善」のサイクルに似ている。
ただし、「最大持続生産量」についての議論はかみ合わないことも多いと山川さんは指摘する。漁獲量、取り残しの資源量など、どの量に注目するかといった方法の違い、長期的な環境変化の影響を考慮するかどうかといった点で、さまざまな「最大持続生産量」が並存しているからだという。
こうした漁業資源の量的管理は1997年にすでに始まっており、今回の漁業法改正で、資源量の評価をもとに管理基準値を定めることが明示された。一方、漁業関係者からは、取ってよい魚の量が年によって変化することは困るという声が聞こえる。新たしい漁業法にこたえるためには、多くの魚種を対象とした漁業や中長期的な環境変化への対応など、いくつかの課題が残っているという。
「反転する環境国家―東南アジアの事例から」
(佐藤仁・東京大学教授)
国が環境を管理すると、かえって地域の人々を苦しめ、自然環境そのものの持続にも悪影響を及ぼすことがあるという「反転」現象を取り上げたのは、東京大学東洋文化研究所の佐藤仁教授だ。
世界の国々では、中央政府による自然の管理が、その領域を拡大してきた。管理の対象は森林や鉱物に始まり、土地や漁業資源、生態系、エネルギーや気候にまで及んでいる。国家による環境政策はこのように「全面化」しており、その際、それに反対する声は聞こえにくい。
環境政策は、それが人間社会をどう変えたのかを問うことが少ない。国による「環境保護」の大義のもとで地域の人々が苦しむ「反転」の例として、佐藤さんは、自然保護区に暮らす先住民を強制的に排除したり、地域のコミュニティーに森林の管理を委譲したりすることを挙げた。
国が、地域のコミュニティーに権限を委譲する管理形態をとることは、民主的で理にかなっているようにみえるが、それが有効に機能するのは、そのコミュニティーに管理の能力がある場合にかぎられる。カンボジアのトンレサップ湖で2013年、従来の漁区が開放され地域の分権管理に移行した際には、管理政策が機能不全に陥った。地域には漁業資源を管理する組織力はなく、担当役人との癒着なども多く報告されたという。
環境の管理は不確実性が高く、国家に権限が集中する傾向にある。環境を守るという、反対意見の出しにくい「温和な大義」の陰で、地域の人々が苦しむことがある。また、国が環境保全のための管理をしようとしても、すでにある開発・生産系の管理と整合しないこともある。国による管理の「反転」を食い止めるポイントは「問題をつくらせない」ことだ。そのヒントは、すでにこの過程を経てきた日本にも多くあるはずだと佐藤さんはいう。
「国内法の観点から見た漁業法改正の評価」
(三浦大介・神奈川大学教授)
神奈川大学法学部の三浦大介教授は、法的な側面からみると、今回の改正で漁業法は公益性、持続的利用が強調されたと指摘する。
たとえば、漁業法で定められている漁業権。大型の定置網を使う定置漁業権、養殖のための区画漁業権、一定の海域を共同で使う共同漁業権の3種類があり、これまでは、いずれも地元の漁協に権利が与えられていた。今回の改正では、定置漁業権、区画漁業権についてはその優先権が廃止され、海域を利用する機会が漁協以外に開かれた。慣習にとらわれず、その海域を利用するのに「ふさわしい者」を行政が選ぶことになる。
その際に大切なのが、その海域が「適切かつ有効」に利用されているかを判断する基準だ。これまで長い期間にわたって漁協が漁業権をもっていたとしても、海域の利用が「適切かつ有効」であるかを判断し、場合によっては別の企業などに漁業権を移す根拠となる透明性の高い基準が求められる。その免許を出す権限は都道府県知事にある。国は基準のガイドラインを示すが、各都道府県はそれに従う義務はなく、地域の発展に役立つ基準を、それぞれの実情に応じて定めていく。
漁業法は、改正で資源管理の性格を強めている。これはまた、科学的な判断にもとづいた広い裁量を行政に認めることでもある。これまでは海域という「空間」を管理していたが、これからは適切かつ有効に「自然」を管理することが求められる。
漁業法と森林法、河川法などとの関連もさらに問われるようになる。「持続性」との整合を図ることも必要だ。三浦教授は、沿岸域の総合管理を担う漁業法という視点から、これらの関係を追究していくことが重要だと強調した。
「国際的な観点から見た漁業法改正の評価」
(牧野光琢・東京大学教授)
世界の水産物需要は、この半世紀で5倍になった。その一方で、水産資源の3分の1は取りすぎの状態にある。東京大学大気海洋研究所の牧野光琢教授は「このままではいけない」と述べ、改正漁業法による日本の漁業についてその情報を広く世界に発信し、世界を変えていくことの必要性を指摘した。
日本では多くの種類の魚をたんぱく源として食べ、しかも小規模な漁業者が多い。漁業が地域の基幹産業になっている場合もあり、その土地の文化や歴史に根づいた独特の食文化を形成している。こうした日本の漁業の特徴はアジア太平洋地域の多くの国々と共通だ。世界全体の漁業者の8割以上はアジアにいる。アジア太平洋の水産業が変われば世界が変わる。今回の漁業法改正を機に、あるべき漁業の姿を日本からアジア太平洋に、そして世界に情報発信していく必要がある。
海域の環境保全は世界の流れだ。生態系に関する科学的な評価によると、現地の人たちが環境や資源を管理している地域では、人間活動による悪影響が少ない傾向にあると指摘されている。オーストラリアの漁業法は、2007年までは漁業をビジネスとしてとらえて資源の持続性を図ることを目的としていたが、その後、生態系への影響、さらに2017年からは社会やコミュニティーを考慮に入れるようになった。
2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の14番目に「海の豊かさを守ろう」が掲げられている。具体的な行動目標として「水産資源の回復・管理」「生態系の回復」「海洋保護区の設置」などが挙げられた。このSDGsがひとつの契機となり、世界の水産政策がひとつの方向にまとまってきていると牧野さんはみている。
さらに牧野さんは、水産政策は、もはや海洋政策全体の一部と位置づけるのが世界の流れだと指摘した。水産政策が食料生産以外に何をどこまで担うのか。気候変動への適応や人口減少と高齢化のなかでの地方創生。これらの課題に、地域政策・環境保全政策と資源管理政策・経済産業政策のバランスをどうとりながら対処していくのか。その点こそが改正漁業法に問われているのだという。
※当日、会場で配布した要旨集はこちらです。
文責:サイエンスライター・東京大学特任教授 保坂直紀